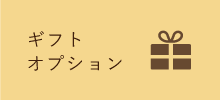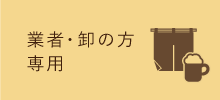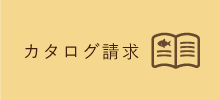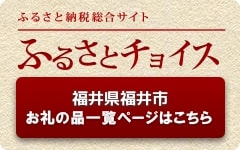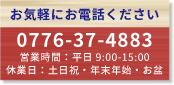ふるさと納税の仕組みをわかりやすく図解で解説。メリットデメリットは?

こんにちは、「越前宝や」の女将・宝山です♪
今日は、ちょっと難しく感じがちな「ふるさと納税」の仕組みを、皆さんにわかりやすくお伝えしたくて記事を書きました。
私も最初は「どういうこと?」って思ってたんですが、図解を使うと本当にスッと理解できるんですよ。
この記事では、ふるさと納税の仕組みをわかりやすく解説して、さらにイメージしやすいように図解もたっぷり使っています。
初めての方でも安心して読める内容ですので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
ふるさと納税の仕組みをわかりやすく図解で解説

まずは、ふるさと納税の全体的な仕組みを押さえておきましょう。
ここでは、寄付から返礼品、そして税金控除までの流れをわかりやすく図解でご紹介します。
これからご説明する2つのポイントをしっかり理解すれば、ふるさと納税の「どうやって得するの?」という疑問もすっきり解消できますよ。
さあ、一緒に見ていきましょう!
ふるさと納税の基本の流れを図解で理解しよう

さて、ふるさと納税の基本の流れって、実はとってもシンプルなんですよ。
01.寄付したい自治体を選ぶ
まずは、自分が応援したい地域や欲しい返礼品のある自治体を選びます。
02.寄付を申し込む
選んだ自治体にネットや書類で寄付の申し込みをします。
申込みが終わると、感謝の気持ちとして特産品が届きます。
03.確定申告かワンストップ特例の申請をする
寄付をしたら、翌年の税金控除を受けるために申請が必要です。
普段確定申告しない方は「ワンストップ特例制度」を使うと簡単でおすすめです。
04.翌年、税金が控除される
申請が受理されると、寄付した分のうち自己負担の2,000円を除いた額が、所得税や住民税から控除されます。
これでお得に地域を応援できるんです。
どうでしょうか、イメージできましたか?
税金の控除が受けられる仕組みをかんたん解説

ふるさと納税の一番のポイントは、「税金を払わなきゃいけない」という大前提を上手に活かして、ちょっとお得に返礼品をもらえる仕組みだってことなんです。
つまり、そもそも税金は誰でも必ず払わなきゃいけないもの。
そこを先に「ふるさと納税」という形で寄付しておくと、実質自己負担2,000円で地域の特産品がもらえるようになります。
寄付した分は翌年の住民税や所得税から控除されるので、結果的に「2000円で返礼品が手に入る」感覚です。

控除を受けるには、
●確定申告をする(自営業、フリーランスや副業してる人向け)
●ワンストップ特例制度を使う(会社員など確定申告が不要な人向け)
このどちらかを選べばOK!
申請をきちんとすれば、翌年の税金がその分安くなりますから、ほんとうにお得です!
しかも、控除の上限額をちゃんと把握しておけば、損せずに賢く活用できます。
(※上限額は年収や家族構成で変わります)
ただ税金を払うだけじゃなく、ふるさと納税の仕組みを使えば、地域も応援できて、返礼品も楽しめて、なおかつ節税にもつながる。
まさに一石三鳥のありがたい制度!
私も最初は戸惑いましたが、一度やってみたら「な〜んだ、こんな感じか♪」って納得しました。
ふるさと納税のメリットデメリットは?

ふるさと納税は、ただお得なだけじゃありません。
利用する前に、どんなメリットがあって、どんなデメリットや注意点があるのかを知っておくことが大切です。
そこで、ここではまず「これがふるさと納税の嬉しいポイント!」という主なメリットを3つにまとめてお伝えしますね。
そして、その後には「うっかりすると困るかも?」という知っておきたいデメリットや注意点もしっかりご紹介します。
良いところも気をつけるべきところもバランスよく理解して、安心してふるさと納税を楽しんでいきましょう♪
ふるさと納税の主なメリット3つ

ふるさと納税の良いところって、実はたくさんあるんですけど、特に押さえておきたいのはこの3つ!
01.好きな地域を応援できる
ふるさと納税の一番の魅力は、自分が応援したい地域に直接寄付ができることです。
たとえ仕事の都合で故郷を離れて遠くに住んでいても、ふるさと納税を通じて地元を応援できるのは嬉しいですよね。
「遠くにいて何もできない…」と感じている方も、寄付によって地域の医療や福祉、子育て支援などに役立てられます。
例えば、両親や祖父母の健康を支える病院や介護施設の充実に貢献できるかもしれません。
うちのスタッフにも、地元を離れて頑張っている子がいるんですが、遠くにいても、こうして故郷に恩返しができるのは、本当に心強いことだなあと私も感じています。
私自身はずっとここで暮らしていますが、スタッフのそんな話を聞くたびに、ふるさと納税の良さを改めて実感しています。
02.お得に特産品がもらえる
ふるさと納税の一番の楽しみは、やっぱり地域の美味しい返礼品がもらえることですよね。
寄付した額のほとんどが税金から控除されるから、実質2,000円の負担で、たくさんの特産品を手に入れられるのは本当に嬉しいことです。
03.税金の控除で節税できる
寄付した金額は、所得税や住民税から控除されるので、節税にもつながります。
上手に活用すると家計にも優しいですよ。
例えば、普段から食べているお米やお魚、お肉を選べば、毎日の食費の節約にもつながりますし、忙しい時や頑張った自分へのご褒美に、普段はなかなか買えないちょっと高級な返礼品を選ぶこともできます。
うちのスタッフの中には、お中元やお歳暮でふるさと納税を活用している子もいます。
どうやら定期的に当店の電子レンジできる煮魚焼き魚セットを贈っているようで、「これが届くと、しばらくご飯に悩まなくて済む~」と親戚から大評判のようです。
必ずある出費に、こういう活用方法もいいですよね!

【3ヶ月定期便】骨取り 煮魚・焼き魚・西京漬 4種8切
【6ヶ月定期便】骨取り 煮魚・焼き魚・西京漬 4種8切
【12ヶ月定期便】骨取り 煮魚・焼き魚・西京漬 4種8切
知っておきたいデメリットと注意点

ふるさと納税は魅力的な制度ですが、利用する際にはいくつか注意したいポイントがあります。
01.寄付額の上限に注意!
年収や家族構成によって控除の上限額が決まっています。
上限を超えると自己負担が増えるので、しっかり確認してから寄付しましょう。
▼ここから上限額をシミュレーションできますので、一度確認してみてください。
>> https://www.furusato-tax.jp/about/simulation
02.返礼品の届くタイミングがバラバラ
急ぎの時には返礼品が間に合わないことも。
人気商品や季節限定品は早めの申し込みが安心ですよ。
03.手続きの忘れに注意
確定申告やワンストップ特例制度の申請を忘れると、控除が受けられません。
仕組みや手続きはしっかり把握しておきましょう。
まとめ

今回は、ふるさと納税の仕組みをわかりやすく図解でご説明しましたが、いかがでしたか?
この制度は、税金の仕組みを理解して上手に活用すれば、地域を応援しながらお得に返礼品をもらえる素敵な仕組みなんですよ。
難しく感じがちなふるさと納税も、図解を使ってわかりやすく知ることで、初めての方でも安心して始められます。
ふるさと納税の仕組みをしっかり押さえておけば、寄付の流れや控除の仕組みもスムーズに理解できますし、メリットや注意点も見逃さずに活用できますよ。
ぜひ、今回のわかりやすい図解と説明を参考に、ふるさと納税を賢く利用してみてくださいね。
これからも地域の魅力を楽しみつつ、賢い納税で暮らしを豊かにしていきましょう!